
その製品、本当に儲かってる? 原価計算における製造間接費配賦の罠
2025年4月13日
質問
「MJSみろく工業」では、A製品、B製品、C製品の3つの製品を製造・販売しています。A製品は標準的な大量生産品であり、B製品およびC製品は、顧客ニーズにあわせて特殊なアレンジが必要となる少量・中量生産品です。製品の製造過程においては、資材・活動準備、段取、検査などの活動に多額の製造間接費が発生していますが、製品の収益性を正しく評価するためには、どのような基準を用いて、各製品に製造間接費を配賦する必要があるでしょうか?
パターン1
各製品の製造数量に応じて配賦する。
パターン2
各製品の加工作業時間に応じて配賦する。
パターン3
各製品の製造に関連する活動量に応じて配賦する。
この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。

|

|
ある製品が売れれば売れるほど利益減少 ~その要因は製造間接費の配賦にあった
「MJSみろく工業」は、売上は好調であったにもかかわらず、ある製品が売れれば売れるほど利益が減少する現象が起こっていました。問題の深刻さに気付いたMJSみろく工業は、コンサルタントに相談したところ、製造間接費の配賦方法に問題があることを指摘されました。製造間接費の配賦が適切に行われていないことで製品の収益性評価を誤り、その結果、製造原価を下回る販売価格設定が行われていたのです。
製造活動の実態に即した製造間接費の配賦への見直しを行ったところ、これまでの製造原価とは全く異なる結果となりました。新たな製造間接費の配賦計算によって、適切な製品の販売価格や販売計画を立てられるようになったMJSみろく工業は、無事に業績の回復を図ることができたのです。
製造間接費の配賦計算に問題あり!?
ある日の経営会議でのことです。
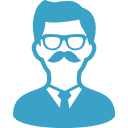
社長
営業部長、各製品の販売状況を報告してくれ
売上はいずれの製品も順調です。特に、A製品を特殊加工したB製品、C製品は人気が高く、販売量が伸びています
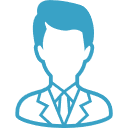
営業部長
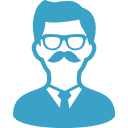
社長
B製品、C製品は販売単価も利益率も高いからな。業績もうなぎのぼりだろう! 経理部長、財務状況について説明してくれ
社長、それが……。売上は伸びているのですが、なぜかC製品が売れれば売れるほど、利益が減少しているようなのです

経理部長
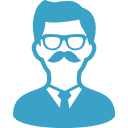
社長
C製品は、もっとも利益率が高い製品ではないのか? いったい何が起こっているというんだ
コンサルタントに相談してみたところ、製造間接費の配賦計算に問題があるとの指摘を受けました。すなわち、各製品に共通してかかっている費用を、各製品に配分する方法に問題があるようです

経理部長
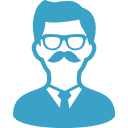
社長
いったいどういうことなんだ!? 早急に原因を解明してくれ!
どうやら、C製品が売れるほど利益が減少していく要因は製造間接費の配賦方法にあるようです。製造間接費をどのように配賦することで、この問題を解消できるのでしょうか。
質問
「MJSみろく工業」では、A製品、B製品、C製品の3つの製品を製造・販売しています。A製品は標準的な大量生産品であり、B製品およびC製品は、顧客ニーズにあわせて特殊なアレンジが必要となる少量・中量生産品です。製品の製造過程においては、資材・活動準備、段取、検査などの活動に多額の製造間接費が発生していますが、製品の収益性を正しく評価するためには、どのような基準を用いて、各製品に製造間接費を配賦する必要があるでしょうか?
▼あなたの思うパターンをクリック▼
パターン1
各製品の製造数量に応じて配賦する。
パターン2
各製品の加工作業時間に応じて配賦する。
パターン3
各製品の製造に関連する活動量に応じて配賦する。
製造した製品数量に応じて製造間接費を配賦する方法によった場合、それぞれの製品の製造にかかる手間は異なるにも関わらず、すべての製品に等しく製造間接費が配賦されてしまいます。これでは、製造の実態を表した適切な配賦とは言えません。
各製品の加工作業時間に応じて製造間接費を配賦する方法によった場合、加工作業時間が長い量産品に多額の費用が配分され、加工作業時間の短い少量・中量生産品には相対的に少ない費用が配分されることになってしまいます。しかし、実際には少量生産品の方が多くの手間がかかってしまうものなのです。
MJSみろく工業は、少量・中量生産品にかかる手間を製造間接費の配賦計算に反映させるため、活動の消費量に応じて製造間接費を配賦することにしました。どういうことかというと……
各製品に関連する活動量を反映した製造間接費の配賦
MJSみろく工業は、これまで各製品の機械稼働時間を基準として、製造間接費総額を各製品に配賦してきました。その結果、機械稼働時間が長くなる量産品に多くの製造間接費が配賦され、機械稼働時間が短くなる少量・中量生産品には相対的に少ない製造間接費が配賦されることになっていたのです(製造間接費の配賦と内部相互補助問題)。しかし、実際の製造プロセスにおいては、少量・中量生産品に多くの手間や追加的な対応が必要となります。MJSみろく工業は、これを反映するような製造間接費の配賦方法への変更を検討することにしたのです。
これまでの製造間接費の配賦方法では量産品であるA製品に多くの製造間接費が配賦され、製造に多くの手間がかかっているB製品、C製品などの少量・中量生産品には相対的に少額の製造間接費しか配賦されていません

経理部長
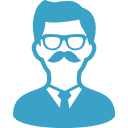
社長
少量・中量生産品には、製造の過程で実際にかかっている費用よりも少ない金額が配賦されるということになるのか
はい。その結果、B製品、C製品の製造原価が小さく計算されてしまい、販売価格設定を誤ってしまっていたようです。C製品にいたっては、製造原価を下回る販売価格設定がされておりました。

経理部長
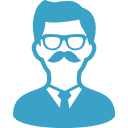
社長
なんということだ…。それでC製品が売れるたびに利益が減少してしまっていたというわけか……
問題に気付いた社長と経理部長は、議論を重ねた結果、製造プロセスの実態を反映した配賦を行うために、製造間接費の配賦方法を次のように変更することにしました。
■従来の方法(機械稼働時間で配賦する方法)
| 合計 | A製品 | B製品 | C製品 |
|---|---|---|---|
|
機械稼働時間合計 1,000時間 |
500時間 |
400時間 |
100時間 |
|
製造間接費総額 1,000万円 |
500万円 |
400万円 |
100万円 |
■新たな方法(活動ごとに異なる配賦基準を適用する方法)
| 合計 | A製品 | B製品 | C製品 |
|---|---|---|---|
|
資材・加工準備活動 750万円 |
400準備時間 300万円 |
400準備時間 300万円 |
200準備時間 150万円 |
|
段取活動 150万円 |
10回 15万円 |
30回 45万円 |
60回 90万円 |
|
検査活動 100万円 |
20時間 20万円 |
20時間 20万円 |
60時間 60万円 |
|
製造間接費総額 1,000万円 |
335万円 |
365万円 |
300万円 |
新たな配賦方法として、間接的な業務を資材・加工準備活動(資材の移動や加工準備作業)、段取活動(加工のための装置の交換作業)、検査活動(製造完了後の検査作業)の3つの主要な活動を特定し、それぞれの活動に要したコストを、関連する基準を用いて各製品に配賦することにしたのです。
その結果、C製品の製造活動に由来する製造間接費は、従来の配賦方法による金額(100万円)の3倍(300万円)もかかっていたことが判明し、C製品の製造原価を相当に低く計算してしまっていたことで販売価格の設定を誤っていたことが明らかとなりました。
この結果をもとに、MJSみろく工業はC製品の販売価格を見直し、販売戦略の練り直しをすることとなったのです。
「製造間接費の配賦と内部相互補助問題」
製造間接費の配賦は、各製品の製造に要した直接作業時間や機械稼働時間を用いて配賦が行われるのが一般的です。しかし、このような方法によった場合、大量生産品に多くの金額が配賦され、少量・中量生産品には少なく配賦されるという、いわゆる内部相互補助の問題が生じてしまいます。少量・中量生産品の製造には、大量生産に比べてより多くの手間が必要になります。直接費に比べて製造間接費の割合が相対的に高く、金額的重要性も高い企業においては、製造間接費の配賦が与える影響について慎重に検討する必要があるでしょう。場合によっては、製品原価や収益性の評価を誤り、誤った販売戦略によって業績を悪化させる可能性もあるのです。これを克服する方法として、活動の消費量に応じて製造間接費の配賦を行う、活動基準原価計算(Activity-Based-Costing: ABC)と呼ばれる原価計算手法が開発されています。
経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。
最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。
皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています
Tweets by mjs_zeikei

