
デジタル給与、解禁で広がる!? デジタル給与とは? 企業に求められる対応は?
2025年5月13日
質問
「ミロク・コーポレーション」の社長は、「デジタル給与」が認められるようになったという情報を耳にしました。「デジタル給与」とはなんのことでしょうか?
パターン1
給与を電子マネーで支払うこと
パターン2
テレワークによる勤務に対して支払われる給与のこと
パターン3
給与明細が電子化されている給与のこと
この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。
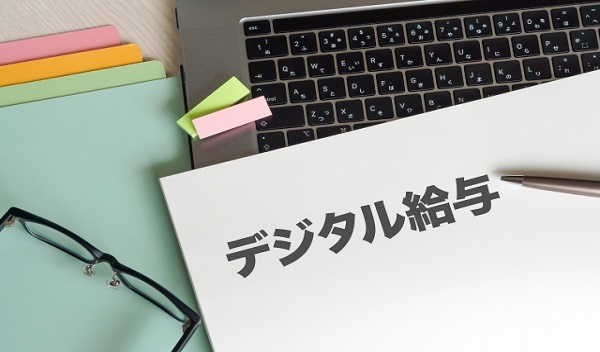
|

|
部門を横断するメンバーでデジタル給与について検討
サービス業を営む「ミロク・コーポレーション」。人事部や経理部、総務部などからメンバーが集まり、デジタル給与の導入に関する検討を行っています。
社長、デジタル給与に関する従業員向けのアンケートを来週実施します

人事部スタッフ
アンケートに添付する資料も準備済みです

経理部スタッフ
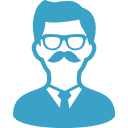
社長
短期間でよく準備してくれたね。よろしく頼むよ
現在、デジタル給与に関する検討に取り組んでいるミロク・コーポレーションですが、1か月前には、デジタル給与という用語を聞いたことのないメンバーばかりでした。
1か月前 ~「デジタル給与」解禁! ……デジタル給与とは?
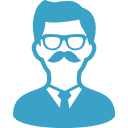
社長
『デジタル給与』が解禁されたという話を耳にしたんだが、『デジタル給与』ってなんだい?
『デジタル給与』ですか? 初めて聞きましたが……

経理部スタッフ
質問
「ミロク・コーポレーション」の社長は、「デジタル給与」が認められるようになったという情報を耳にしました。「デジタル給与」とはなんのことでしょうか?
▼あなたの思うパターンをクリック▼
パターン1
給与を電子マネーで支払こと
パターン2
テレワークによる勤務に対して支払われる給与のこと
パターン3
給与明細が電子化されている給与のこと
デジタル給与は、電子マネーによって支払われる給与のことをいいます。
従来、従業員への給与の支払方法としては、現金での支払または銀行口座などへの振込による支払のみが認められてきましたが、法改正により、給与のデジタル払いも可能となりました。
デジタル給与は、電子マネーによって支払われる給与のことをいいます。テレワークではデジタルツールを利用することが多いものの、テレワークによる勤務に対して支払われる給与をデジタル給与と呼ぶわけではありません。
デジタル給与は、電子マネーによって支払われる給与のことをいいます。給与明細を電子化しても、デジタル給与と呼ぶわけではありません。
多様化する送金サービス
(♪♪-スマホの通知音-)「あっ、すみません! スマホをマナーモードにするのを忘れていたわ

経理部スタッフ
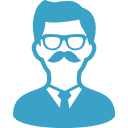
社長
アプリの通知かい?
はい。さっき同僚とランチに行った時、お店での支払は私が立て替えたんです。立て替えた額を電子マネーで送金してもらったんですよ

経理部スタッフ
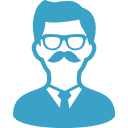
社長
ピッタリの現金を持ち合わせていなくても、電子マネーを使えばその額を送金できるわけか
あっ! 『デジタル給与』も、同じかもしれませんね

経理部スタッフ
給与のデジタル払いが解禁
厚生労働省のウェブサイトを見てみましょう。……思ったとおりだわ! デジタル給与というのは、電子マネーで支払う給与を指すようですよ

経理部スタッフ
従来、労働基準法とその施行規則では、給与の支払方法として、現金での支払または銀行口座などへの振込による支払のみが認められてきました。
しかし、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進んだ昨今では、給与を電子マネーで受け取りたいというニーズも想定されます。こうした変化などを背景に、労働基準法施行規則が改正され、2023年4月から、賃金のデジタル払い(電子マネーによる給与の支払)が新たに認められるようになりました。企業が従業員の同意を得た場合には、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動によって賃金を支払うことができます。
給与の支払方法の選択肢が広がったということですね

経理部スタッフ
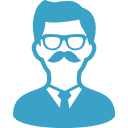
社長
時代の変化を感じるなあ。……資金移動業者というのはなんだい?
先ほど私と同僚が使ったような、いわゆる『○○Pay』などのキャッシュレス決済を運営する事業者を指すんです

経理部スタッフ
指定資金移動業者は、厚生労働省のウェブサイトで公表されています。
普段の生活で電子マネーを頻繁に使うなら、給与も電子マネーで受け取れれば便利かもしれませんね

経理部スタッフ
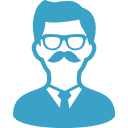
社長
そうだね。しかし、私は電子マネーを使っていないから、電子マネーでしか給与を受け取れないのは困るなあ
その心配はないようですよ

経理部スタッフ
デジタル払いは、給与の支払方法の選択肢の1つです。企業や従業員に対して給与のデジタル払いの導入を強制するものではありません。
企業によるデジタル給与の導入は任意で、従業員がデジタル給与の導入を希望しても、これに応じる義務はありません。
また、企業がデジタル給与のしくみを導入しても、個々の従業員の同意がなければ、給与のデジタル払いを行うことはできません。デジタル払いを導入した企業でも、引き続き銀行口座への振込により給与を受け取ることも可能です。従業員の希望により、給与の一部を電子マネーで受け取り、残りを銀行口座で受けとることもできます。
デジタル給与のメリットとデメリット
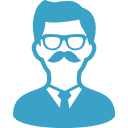
社長
当社でも給与のデジタル払いの導入を検討してもいいかもしれないね
給与のデジタル払いを導入すると、どんなメリットがあるんでしょう?

経理部スタッフ
給与のデジタル払いを導入することには、次のようなメリットがあります。
<企業側のメリット>
・資金移動業者への送金手数料は、銀行の振込手数料よりも低いことが想定されるため、手数料を削減できる可能性がある
<従業員側のメリット>
・給与の一部または全額を電子マネーで受け取ることで、チャージの手間が省ける
・給与の受取に銀行口座と電子マネーを併用すれば、給与の管理や仕分けを行いやすい
一方で、次のようなデメリットもあります。導入を検討する際には、メリットとデメリットの両方を勘案する必要があります。
<企業側のデメリット>
・給与の支払方法が増えることで、給与支払に係る業務量が増える
・給与システムの改修や機能追加が必要な場合がある
<従業員側のデメリット>
・デジタル給与では、口座に上限額がある(口座の上限額は100万円以下に設定される)
・セキュリティ対策やスマートフォン紛失時の対策を十分に講じておく必要がある
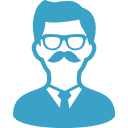
社長
デジタル給与の概要やメリット・デメリットを従業員に周知したうえで、導入を希望する従業員がどの程度いるか、把握するほうがよさそうだ
そうですね。資料を作成して、アンケートを取りましょう

経理部スタッフ
デジタル給与の導入に向けた対応
給与のデジタル払いを導入する場合、企業と従業員の間で労使協定(※)を締結することが求められます。労使協定には、給与のデジタル払いの対象となる従業員の範囲や、取扱指定資金移動業者の範囲などを記載します。
そのうえで、デジタル払いを希望する個々の従業員に対して、口座上限額などの留意事項を説明し、デジタル払いで受け取る給与の額や、資金移動業者口座番号などを記載した同意書(※)を個別に提出してもらう必要があります。
さらに、企業の就業規則(給与規程)も改定しなければなりません。
(※)労使協定や同意書の様式例は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
こうした諸手続のほか、給与のデジタル払いを導入するにあたっては、給与システムがデジタル払いに対応できるかどうかを確認することも欠かせません。給与システムによっては、改修や機能の追加を要することも想定されます。この場合、改修や機能の追加に係るコストと手間がどの程度になるか、早期に把握するほうがよいでしょう。
また、給与システムと会計システムが連携しているケースが多いと考えられます。システム間の連携に係る設定や、会計システムにデータを取り込む方法・タイミングなどを、事前に確認する必要もあります。
デジタル給与の導入を検討するには、人事部、経理部や総務部など、各部門が横断的に協力する必要がありそうですね

経理部スタッフ
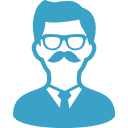
社長
各部門からメンバーを出して、定期的にミーティングを行おう。私も向学のために電子マネーアプリをインストールしてみるか
「デジタル給与」
キャッシュレス決済の普及などを背景に、給与のデジタル払いも認められるようになりました。
給与のデジタル払いを導入するには、労使協定の締結や従業員の個別同意などが求められます。給与システムがデジタル払いに対応できるかどうかの確認も必要です。
なお、デジタル給与(賃金のデジタル払い)についての各種情報は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されていますので、そちらもご確認ください。
経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。
最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。
皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています
Tweets by mjs_zeikei

